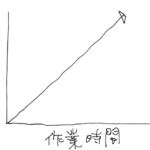メディアアーティストにして研究者である落合陽一氏の「魔法の世紀」を読みました。
十分に発達した科学は魔法と区別がつかない、20世紀の「映像の世紀」から「魔法の世紀」へ――次世代と言われるIoTは予測された通過点でしかなく、その先にあるものはイメージの中で起こっていた出来事が、物質の世界へ踏み出していく時代である。コンピュータが自然と人工物とをとりなして、新たな自然観を開いてゆく。
芸術や科学、とりわけコンピューターの歴史を紐解きながら、21世紀に向かっていく新しいデジタルの時代を予見する。私達はコンピュータのミトコンドリアと化すのか、コンピュータがミトコンドリアなのか。我々が生きている間に実現するかはともかくとして、レイ・カーツワイルの思想を噛み砕いたようなある種の未来予想図としては、かなり精度が高いように感じる面白い本でした。
しかしコンピュータの歴史や概論の説得力に比べると、芸術や文化史のまとめ方は、少し大雑把に感じる部分もあります。コンテンポラリーアートを「文脈を理解する人々のゲーム」として捉え、自身のメディアアートや研究を「原理のアート」を指向するものとして慎重に分けているようでした。ただ、それ以上の言及に乏しく、芸術が社会的に果たしてきた機能については触れられていません。また、芸術が表現するものの一つに「時代性」がある以上、それは社会全体が文脈のゲームになっているという一面を、先鋭的に反映しているのではないか。
「原理のアート」とは一回性の経験であり、「コンテンポラリーアートの中にメディアアートが溶けて」しまったように、資本主義経済の中で旧来のエンターテイメントとして「溶けて」しまうものではないだろうか。あるいは、それは著書の中でも重要性が触れられているデザインやコミュニケーションの概念に近いもの、そういった文脈の中でたやすく貨幣価値に変換されてしまう(著書の中で触れられているディズニーのコングロマリットやキャメロンの映画のように)のではないかと感じました。
仕組みを理解しなくとも使用できること。さらにいえば、仕組みそのものを子供でも変えていけること。それは70年代のDynabook構想以後のコンピュータ、そして「魔法の世紀」における重要な要件でしょうが、そこにおいては「文脈のゲーム」は解消されうるのでしょうか。「魔法の世紀」においてすら、魔法を理解するプレーヤーたち(それは人間ではないのかもしれませんが)による文脈のゲーム化は避けられないのではないか。そもそも、この本を手に取るような人は十分に「意識が高い」「ある文脈上のプレーヤー」と言えるのではないだろうか。
などなど。
概念を拡大すれば、惑星そのものを計算し、究極のところ宇宙そのものを完璧にコンピューティングするということでしょうか。なんだかどこかの銀河鉄道の機械化母星を思い出させます。
ともあれ、私はここに描かれた希望のイメージについて概ね肯定的であり、様々な点で勉強させられ、敬服しました。帯に書かれている富野由悠季さんの言葉「落合陽一はニュータイプだろう」は至言です。この言葉で腑に落ちる、という感じすらいたします。落合氏はこれからもニュータイプであるが故の苦悩と希望を、古典と化したアニメの主人公のように見せてくれるのではないかと期待します。私たちは自分が生きる時代の、不幸というものの本質を捉えそこないがちだからです。
ちなみに私は、タイトルと本書の装丁からアンドレ・ブルトンの魔術的芸術を想起いたしましたが、原理のアートの例として、ジャクソン・ポロックのアクション・ペインティングに関する下りはあれど、シュルレアリスムなどは特に関係ありませんでした。

魔法の世紀 落合陽一 (著)〈amazon〉